これまで撮りためている360度の写真があります。。。
もちろん、360°バーチャルツアー用であったり、360VR(VRゴーグル)用であったりです。
パソコンやスマートフォンで見る分には、3Dである必要性はありません。
今のところ、3Dを映し出せる(立体的な画像を出せる)モニターは、民生機器としてないでしょう。
あったとしても、出力側のアプリケーションを指定されるものだと・・・思われます。
ただ、普通の360度写真は深度(Depth)の情報がありませんので、筆者みたいに、何度も何度もVRゴーグルで見ていると違和感みたいなものが芽生えてきます。
立体感が乏しい(現実に、立体のデーターはない)ということですね。
なぜ、立体感が欲しいのか?
単純に、距離感の表現ができないからです。
普通の360度パノラマ写真でも広い・狭いは何となく分かるのですが、もっとリアルな距離感みたいなものも分かったら嬉しいな。
ということを前から思っているので、時々、気が向いたときに試しています。
お客様から、実際、3Dを求められているか?というと、そんなことはありません。
今のところ、VRゴーグルと、その各種機能で足りています。
ただ、視聴されているお客様(見て頂いている一般の方)からは、時々、痛いお言葉があるんですよねー😊
「あれ!?歩けないの?」
っというお言葉を・・・💧
ごめんください。歩けないんです・・・。
とお答えするしかないのですが、心の中では”このVRでは”っと言いたいのですね。
久々に、ガッツリと調べると「AppleのDepth Pro」!?
すみません。。。
Appleの製品、昔は使っていましたが、それなりの何かが無くなってしまいましたので、今はiPadだけです。
iPhoneなら空間ビデオとかいうのが撮れたりするようですね。
多分、そこに関係しているのではないかと思うのですが、Appleさんが出している技術があるようです。
さらに、そこを掘って行くと、このDepth ProをWinで動かせるようです。
これは・・・
試すしかありません。
ちなみに、全天球型360度写真の深度(Depth)を綺麗に生成するのは難しいんだろうな。。。
(なんか、AIで通りかかった記憶はあるのですが・・・)
Anaconda
まずは、これが必要なようです。
Miniconda3-latest-Windows-x86_64(昨日のVer)の方では動かなかったので、面倒くさいので、Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64(昨日のVer)を入れると、なぜかサクッと動きました。
(コマンド画面が開くだけですけどー)
depth_pro.py
ちなみに、Python 3.13 (64-bit)をインストール済みだったので、そのまま、ネットの情報を元に、
depth_pro.py をダウンロードして環境を整えます。
全く活用できていないのですが、AIにコーディングとかやり方を教えて貰うと、Pythonさんを使ってできる提案をくれることがあります。
回答を読んで、「まじか!?Python!?」と思うこともありますね😊
さらに、細かい情報をググり調べテストする・・・
上記で深度マップのファイルを生成してくれるようになるのですが、あくまで、サンプル出力です。
必要な形にして貰うのに、調べる時間が必要でした。
本当は、カラー(24bit)で出したかったのですが、欲しいカラーは特別な仕様なのでダメっぽいです。
グレイスケール(8bit)しか使えないという悲しい感じです。
出力された深度(Depth)マップの画像を加工する
全天球360度写真のパソコンで見る時の形で代表的なものは、W:H=2:1の形式です。
左右の端と端が、くるんと巻かれてくっついて、360度の球体になるのですね。
案の定、出力された深度マップの画像の端と端の濃淡が異なりますので、ここは、サクッと加工します。
加工をしなくても見ることはできると思うのですが、変に立体感が出ると「なんじゃこりゃ?」という印象を与えてしまいますので、変な部分が見えてもいいけど、目立たなくはしたいところですね。
次は、制作ツール側での調整が必要なのかー(涙)
さて、サクッと仕上げ~・・・
とはなりませんでした。orz
翻訳しながら読み進めて行くと、深度マップもいろいろな最適解があるようです。
つまり、ツール側の最適解で例えば1という数値になっていても、今回の深度マップでは異なる数値が必要になるようです。
何度も何度も数字を入れては、VRゴーグルを持って動くという果てしなく無駄に無駄に思える作業です💧
ちなみに、結局、ダメなこともあるので、完全骨折り損ということも開発では多々あります。
この調整作業で分かったのは、撮影時のレンズの高さで数値も変わるということでした。
空撮360度のパノラマ写真をテストに混ぜておいてよかったです。
でないと、本番で作って欲しい!となった時に何が悪いのか切り分けが大変になるところでした。
ちょっとだけ書かせて頂くと、大きさを超小さくして、設定をイレギュラーにすると、あら不識💛
めちゃくちゃ可愛いミニチュア風の風景が広がって失敗なのですが、「これはっ!めっちゃ、いい表現だー!」と嬉しくなりました😊
ほぼ完成(調整で2日かかり・・・)
何といっても、今回の apple Depth Proを使うのが初めてで、各種数字に何を当てはめると、いい感じになるのか分からないところから進めています。
VRゴーグルも、さまざまな表現になる上に、それを数分おきに見ていると、眼が変になってしまいます。
大部分が休憩・他作業となるのですが、珍しく2日かかりました。
(ただ、同じ技法で作るなら、半分以下の工数で作れると思います)
今回のサンプルは、「工場の現場の通路」「広い作業場」「琵琶湖の風景(三脚)」「琵琶湖の風景(空撮)」の4っで試してみました。
- 工場の現場の通路
やばいくらいの立体感。今までの360度パノラマ写真をVRゴーグルで見るのとは違うなと。
手前の装置や現場の通路の向こう側まで3Dならではの伝わり良さです。 - 広い作業場
多分、縦x横:50mx30mくらい?の場所です。実際、端の方は別の作業用に区画を割っているので、25mくらいが横幅という感じです。
見渡すだけなら、3Dと言われなければ分からない立体感です。
ただ、天井の高さや、奥行き感が違いますね。何となく臨場感溢れるというか・・・ - 琵琶湖の風景(三脚)
非常に見通しが良い場所なので、同じく立体感については分かりにくいですね。
ただ、広々としているので、VRゴーグルを装着したまま、座ってみました。
うーん、コレは癒しとかリフレッシュにいいかもです!
地面との高さが変わると、これだけ自然な感じになるのですね。 - 琵琶湖の風景(空撮)
普通の360度写真をVRゴーグルで見るのと一番変わらない感じでした。
古い写真なので、Mavic Mini初代。高度は、多分、80mとかそんなものです。
ただし、空撮なので水平方向に邪魔な壁や什器はありません!
スイスイーっと、スーパーマンになった感じで遊泳できます😊
(子供にはウケそうかな?)
ざっくりは、こんな印象です。
360度パノラマ写真からの深度マップ3Dはおすすめか?
はい。
見せる場所を選びさえすれば、超圧倒の表現はおすすめです!
「見せる場所」と書かせて頂いた理由は・・・
3D化するため、本来、見えていない部分の画像を周辺の画像から引き延ばして使う感じになります。
例えば、太めのロープが下がっている部分を見ると、ロープから後ろ側には何か紙とか壁が張り付いているような・・・な見え方です。
これは、左目と右目で見える範囲が違うので、左目は左側の貼り付け・右目は右側の貼り付けという感じですね。(ただし、ロープの距離にも関係します)
歩くことができるのですが、同じように写真として写り込んでいない部分は引き延ばされて奥行きがなくなります。例えば、机の向こうは、机の高さです。
ちょっと、書いている意味が分かりにくいでしょうね・・・
つまり、”普通の”360度パノラマ写真のバーチャルツアーやVRツアーがある上で、もっと、異なった楽しみや伝え方がしたい場合は、深度マップ3Dも加えてください。
“普通の”を見れる上で、イベント用に・学習用に・遊び用にという使い方ですね。
超圧倒の表現になる理由は、奥行きが出せる=近い・遠いが出せる=空間に様々なモノを出せる=新しい感じのゲームや、新しい感じの説明にできる!ということです。
例えば、空中にフワフワとした風船が浮いているとします。
普通の360度バーチャルツアーやVRツアーでは、その風船を真上に飛ばすには、水平を0度としたとき、-90度の角度しかできません。手でとれる範囲なのか?手は届かない範囲なのか?は難しいですね。
(何かしら代替え方法はあるかもですが・・・)
例えば、3D化していると、「子供でも手に届く感じ?高さ100cmくらい?できますよー😊」という感じになります。
向こう側から目の前に突進してくるような何かをリアルに表現することもできるでしょう。
こんな風に、すぐに思いつくことだけ思い浮かべて想像しただけで・・・
またも、やばい領域に片足を踏み込んでしまった気もします・・・💧

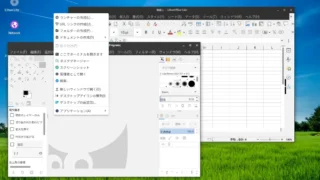





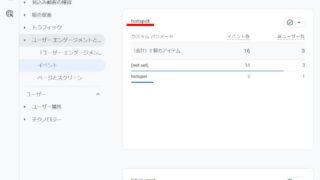
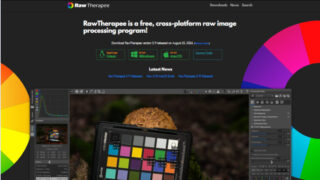




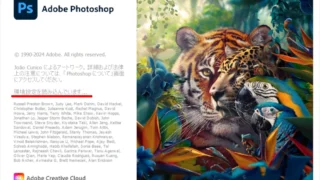









コメント